 公正証書作成の手引きTOPページ メールフォーム 料金表 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公正証書(金銭債務) |
|||||||||||||||||||||
公正証書とは原本は公証役場に保管され、債権者には正本が、債務者には謄本がそれぞれ交付されます。 このように原本は公証役場に保管されるので、たとえ当事者が正本や謄本を紛失したとしても効力が失われることはなく再交付を受けることも可能です。 そして、金銭消費貸借契約による貸付金 や 離婚に伴う養育費の給付など将来に渡って支払いが継続する「金銭債務」については、「強制執行認諾約款」の付いた公正証書 にまでしておけば、強制執行力のある強力な書面となります。 つまり、債務者が将来契約通りの支払を怠った場合には、裁判をしなくても 強制執行(差押)を裁判所に申し立てることが可能になるのです。 「強制執行認諾約款」 とは、債務者が、支払いを怠った場合には直ちに強制執行を受けることを了承している旨の文言をいいます。 具体的には「債務者は、本公正証書記載の金銭債務を履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」 という文言が 公証人によって 記載されます。 また、公証人に虚偽の申告をして実態と違う公正証書を作成させることは、公正証書原本不実記載罪に問われる可能性がありますので、くれぐれも注意ください! 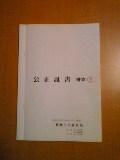 公正証書作成に必要な書類等ⅰ 運転免許証と認印 ⅱ パスボートと認印 ⅲ 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印 ⅳ 印鑑証明書と実印 ⅰ~ⅳ のどれかで良いです。 ただし、代理人が出頭して作成する場合には、代理人自身の上記ⅰ~ⅳのどれかの他に、本人の委任状 が必要となります。 そして、委任状には 本人の実印 が押印され 印鑑証明書 が添付されている必要があります。 ですから、委任状は、委任状と公正証書原案(公正証書作成のための合意書)の内容の写しを、ホチキスでとめて契印を押して提出します(当事務所にご依頼頂いた場合は委任状もお付けいたします)。 なぜなら、当事者が、法的にどのような内容の合意をし、どのような内容の公正証書を希望しているのかを公証人に正確に伝える必要があるからです。 『どのような内容の公正証書を作成するか』 こそ が重要なのです! 公証人は、違法な内容については、チェックをしてくれます。しかし、公証人は中立的な立場ですので、どちらかに有利または不利になるような誘導は基本的にはしてくれません。 ですから、あらかじめ法的に内容を吟味した公正証書原案を持っていかないと、話の上手い債務者が主導権を握り、債務者に都合の良い内容の公正証書が作成されてしまったり、逆に債務者が現場で煮え切らない態度を繰り返し、公正証書の作成手続自体が進まない可能性もあります。 公正証書を作成する場合は、失敗しないためにも事前に専門家に相談したり、公正証書原案(合意書)の作成を依頼してから、公証役場へ出頭し公正証書の作成に臨むことが賢明です。 公正証書を作成する目安また、離婚給付公正証書については、子供に対して月々の養育費の支払がある場合など、将来に渡って金銭を給付する債務が残ってしまう場合に作成することが多いでしょう。 では、金銭消費貸借契約などにおける「ある程度金額の大きな貸付け」とはどの程度でしょうか? 債権額が 60万円 を超えているか否かがひとつの目安になるかと思います。 なぜなら、60万円以下の債権の場合には、簡易裁判所の少額訴訟 という制度が利用できるからです。 少額訴訟制度を利用すれば、原則1回の期日の出頭で迅速に裁判を終わらせ判決をもらうことができます。 ですから、少額訴訟を利用できる場合は、公正証書を作成しなくても、迅速に確定判決を得ることで、強制執行が可能となるのです。 ただし、少額訴訟も裁判である以上、勝訴判決を得るためには証拠が当然必要です。 証拠として、内容の整った 金銭借用書など の契約書がないと、期待通りの判決をもらえない可能性がありますのでご注意ください。 公証役場に支払う手数料・印紙代・その他諸費用・ 公証人に支払う 作成手数料
・収入印紙代 金銭貸借の公正証書原本には原則として債権額に応じた収入印紙の貼付も必要です。収入印紙の額についてはこちらを参照 収入印紙の額(印紙税) なお、金銭貸借と違い、離婚給付公正証書には、収入印紙の貼付は不要です。 ・その他の諸費用 正本/謄本代(1ページ250円×ページ数) ・特別送達代(送達手数料1400円+切手代)・送達証明(250円)・執行文付与(1700円)といった諸費用がかかります。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【参考】 執行文の付与・送達証明の交付あまり難しく考えずに、以下の解説は参考程度にお読みください。 ・「送達証明」とは、公正証書証書完成後に債務者に謄本が確かに送達済みであることの証明書をいいます。 ・「執行文」とは、強制執行できる状態であることを公証するために、公証人が付与する文言のことをいいます。 【送達証明の交付】 送達証明の交付は、債権者本人かその代理人が証書を作成した公証役場で、「公正証書謄本等送達証明申請書」に記入して行うことになります(費用は250円です)。 【執行文の付与】 執行文の付与も、証書を作成した公証役場で、「執行文付与申立書」に記入して行うことになります。 執行文には 、①単純執行文 ②事実到来執行文 ③承継執行文 の3種類があります。 通常の場合、相手が支払を怠った時の執行文は①の単純執行文で足ります。 すなわち、請求が債権者の証明すべき事実の到来に関係しない場合で、かつ当事者に変更がない場合に付与される執行文が単純執行文ということになります(費用は1700円です)。 単純執行文については、債務者に公正証書謄本が到達してから1週間程度の期間を経過した後であれば、あらかじめ付与してもらっておくことも可能です。1週間程度というのは謄本到達後に債務者から異議が出る可能性を考慮した期間です。 単純執行文は正本の末尾に「債権者甲は、債務者乙に対し、この公正証書によって、強制執行ができる」旨の文言が付記されます。 単純執行文と違い、事実到来の前に執行文の付与を受けることはできません。 事実到来執行文の場合、通常の単純執行文に加えて、事実の到来(条件の成就)の事実と理由が確認されたことが付記されます。 当然ですが、承継前に承継執行文を付与してもらうことはできません。 債権譲渡や相続などにより債権者が変わった場合などは、これにあたります。 通常の単純執行文に加え、承継のあった事実と理由が確認されたことが付記されます。 執行文の再度付与の手続とは、例えば、一旦強制執行をしたものの、債務者に新たな財産が判明したため平行して新たな財産についても強制執行をするとき等に必要になります。 |
|||||||||||||||||||||
お申込み・お問い合わせ  事務所概要(プロフィール) 不倫の示談書・不倫の誓約書 2025 . 6. 1 更新 |
|||||||||||||||||||||